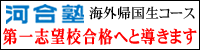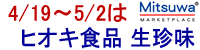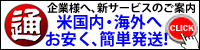シカゴの学校・教育・お稽古・英会話:教育座談会
■
第七回教育座談会:大学進学を見据えた高校生活 経験者からのアドバイス
第七回教育座談会が2025年5月12日にアーリントン図書館にて開催されました。定員15名のところ、33名の方にご参加いただきました。今回は、アメリカの大学に進学された現役大学生とその親御さん、日本の大学に進学された現役大学生の方々にお話をお伺いしました。そして後半は、河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザーより、帰国生大学入試についてのプレゼンテーションを行っていただきました。

<これまでの座談会の内容はこちら!>
MC:それでは、さっそくアメリカの大学進学について、実際にアメリカの高校から大学へ進学された2名の方のインタビューを上映いたします。
MC:それでは、アメリカの大学に進学された、また進学される予定のお子さんのいらっしゃる親御さんにお話を伺いたいと思います。まずは自己紹介からお願いします。
駐在のEビザで滞在しております。子供が8年生と6年生の時に渡米しました。それ以前も別の国でインターナショナルスクールに通っていましたので、英語については心配がない状態でした。現在上の子がシカゴ大学の2年生、下の子がGlenbrook
South 高校のシニアで、カリフォルニアのUCLAに進学します。我が家は二人とも奨学金で学費を全額いただいておりますので、現在は学費の心配はありませんが、以前は色々と調べましたので、分かる範囲でお伝えできればと思います。
MC:ありがとうございます。それでは、大学や学部はどのように選ばれたかを教えていただけますか?
我が家はたくさん大学見学をしました。例えば子供のスポーツの遠征で他州に行った場合は、その周辺の大学を選んで見に行きましたし、下の子は日本に帰国する予定だったので、ロサンゼルスとニューヨークに英検を受けに何度も行きましたので、州立の大きな大学や私立の小さなリベラルアーツの大学を見に行きました。リベラルアーツというのは大学院がなく、教授が4年間学部生をしっかり見てくれます。大学の学費を教授の研究費に注がずにしっかりと学生に使ってくれるので、その後の大学院への進学率が高いという特徴があります。都市型の大学、郊外の大学によってキャンパスライフも変わってくるので見に行った方がよいと思います。始めは疲れるなと思ったりしたのですが、だんだん慣れてくると思います。私のお勧めはカレッジタウンを見ることです。カレッジタウンを見るとどんな大学生活を送れるか、子供に合うかなどが分かっていいと思います。学部についてですが、我が家はどちらも理系でMolecular
Engineering(分子工学)とBiochemistry(生化学)です。学部はリサーチの機会があるかどうか、大学院に進学するのにいい大学かなどを考えながら選んでいます。
MC: 大学によっても違うと思いますが、大学入試前後に覚えてた方が良いスケジュールについてはいかがでしょうか?
高校で説明があると思いますが、気を付けた方が良いかなと思うのが、スポーツをやっているお子さんはアメリカの大学進学に有利なのですが、もし少しでもスポーツ推薦で大学を考えていらっしゃるのであれば、ソフモアが終わった夏休みにコーチと直接話せる日(解禁される日)を忘れずに覚えておいたほうが良いと思います。スポーツによって違いますが、その日からコーチに連絡を取っても良い、もしくはコーチから連絡が来る場合あります。
あと、高校の成績はどの大学に行くにも大事なのですが、11年生(ジュニア)の成績が最重要になってきます。そこでしっかりAをとっていく。簡単な科目ばかりでストレートAというよりは、APクラスをたくさん取ってAをとっていくのが大切だと思います。ジュニアが終わった夏休みはエッセイに全力を注いだ方がよいと思います。
MC:大学進学のための課外活動、クラブ活動、ボランティア活動について教えてください。
上の子は、アーティステックスイミング(シンクロ)が得意で、全国大会に行ったりもしたのですが、高校の水球もやっていて、アスリートとして大学に行くことも考えていました。ジュニアが終わった夏にある工科大学の水球のコーチからお話をいただきまして、それだけシンクロの経験があれば水球で来てほしいと言ってくれました。結局は行かなかったんですが、コーチからオファーがあった場合は、申し込みやエッセイなどすべてコーチが手伝ってくれました。その時は数学のCalculusが終わってAP Statsを取ろうとしていたんですが、そのコーチは工科大学のような高いレベルを目指すのであれば、その学校で一番難しい数学をとったほうがいいと教えてくれました。数学の選択はすでに終わっていたんですが、学校に連絡をしてMultivariable
Calculus &Linear Algebraという一番難しい算数のクラスに変えました。数学が得意でMITとかカルテックに行こうと思っている人は、やはり自分の高校の中で一番難しいクラスを取ることが大事なんだなと思いました。
下の子は、上の子と同じようにやっていたプラス水泳もやっていました。イリノイ州で公式に認められているスポーツIHSA(Illinois
High School Association)の種目であれば、すべての大学に部活があるので、それをやるのはすごくいいと思います。その部活でキャプテンをしたり、アスリートの中で一番成績のいい子がもらえる賞があるんですが、そういうのを持っていると強力なので、下の子はそういうところが認められたのかなと思っています。スポーツも大事ですが、文科系のクラブも大切で、スピーチとかジャーナリズムをやっているとエッセイを書くときに役立つと思います。スポーツは結果だけを書けばいいですが、文科系であれば色々書けて幅が出るのですごくいいと思います。
MC:大学進学について、学校関係者、カウンセラーやコーチのサポートはありましたか?
スポーツについては、種目にもよりますが、バーシティーチームに入っている子達は、だいたいクラブチームにも入っていますよね。ですので、クラブチームのコーチが積極的に助けてくれる場合もあります。水球の場合は、USA
Water Poloが積極的に手伝ってくれて、この試合に行くと今日はスカウトが来てるよといった情報を教えてくれたりしました。
MC:ボランティアはいかがですか?
下の子は高校のクラブでボランティアのリーダーをしたり、夏休みに1週間キャンプに行って貧しい人を助けたりもしていました。でもこれは全部やらなければいけないということではないと思います。お子さんの情熱があるものに全力を注げばよいと思います。
MC:大学進学に必要な科目について教えてください。
これは大学に入ってから気づいたことですが、ジュニアでAPクラスをいくつ取っているか、そしてその成績がどうなのかというところはとても大切です。、シニアで数学と英語のどの程度のクラスを取っているのかも見られると思います。リベラルアーツ系の大学では、理系と文系両方のレベルを見たいのだと思います。ジュニアでAP
Englishをとっていて、シニアで取らない人もいると思いますが、そこはリベラルアーツは学びたいから学ぶ、シニアでもAPをとるというのは見ていると思います。
MC:APをたくさんとることについてどう思われますか? APが難しくてよい成績が取れない場合もあると思うのですが。
やはり11年生(ジュニア)でAを揃えたいですよね。その科目を決めるのが10年生(ソフモア)の冬ぐらいだと思いますが、そこで戦略を練った方がよいと思います。上の子の場合はジュニアでAPクラスを5個取るかどうか迷いました。た。でもAPクラスの全部がBになるとか、APテストで全部3になるとかを考えるとリスクが高いので、どれを辞めるかを考えました。その頃には理系に行くというのが分かっていたので社会のAP
US Historyは宿題も多くて勉強時間がとられるので、これを辞めれば他の科目に勉強を注げると思いました。ソフモアの時にAP
Euroを取っていたので、社会でそんなにたくさんAPをとることはないかなと思って、思い切って普通のクラスにしました。それによって他の科目の勉強が出来たのでうまくいったかなと思っています。
MC:日本の大学の進学も考えられたということですが。
うちの子は、本当はアメリカの大学に行きたいのですが、やはりお金の問題が心配だったので、日本で英語で受けられる大学を受験しました。上の子は慶応のSFCと上智、下の子は慶応のパールを受けました。たしか上智はAPの指定があったと思います。数学も結構厳しくて入試前にCalculus
BCをジュニアまでに終わっている必要がありました。東大にも英語で受けられる学部があったと思います。SATのスコアの指定とCalculus
BCの推奨はあったと思います。
MC:進学の為にやっておいてよかったことはありますか?
スポーツのほかには、個人のリサーチをやっていました。それが結果的に今やっているリサーチを大学でこのようにやっていきたいですといったエッセイを書くことにつなかったのでよかったと思います。
MC:早めの対策といったところではいかがでしょうか?
フレッシュマン(9年生)からオーナークラスを取ろうと思うと中学の先生の推薦が必要になったりするので、中学から準備する必要がありますね。
MC:留学生が受給可能な奨学金を教えてください。
日本からいただけるアメリカに留学する学生に対する奨学金で有名なのが柳井・笹川財団で、学費・寮費・食費その他すべてをもらえるというものです。ですが、ハーバードやケンブリッジに受かってももらえなかったという人は何人もいるので、運と言いますか宝くじに当たるようなイメージの方がいいと思います。奨学金
| JASSOとか日本の高校に通っている子達はもらえてもアメリカ在住だともらえないという奨学金も結構多いんですね。en
(一般財団法人エン人材教育財団)は文系のお子さん中心ですが最近少しづつ増えてきています。しのはら財団というのは人数が少ないようですが、うちの子でも対象だと言われました。とあとは、ニューヨークの日系人のJohn
and Miyokoという財団もあって学費だけでもカバーできるのかと思います。
MC:帰国子女の場合の日本の大学についてはどうですか?
国際基督教大学(ICU)はアメリカ国籍をもっている学生だけに奨学金をオファーしていると思います。日本の大学はウェブサイトも細かく載っていますので、そちらで確認されるといいと思います。 慶応は帰国生枠ではなくグローバルAOというので受けたので入試も英語だけですし、すべてオンラインで終わってしまうので英語ができるお子さんにとっては申し込みやすいと思いました。奨学金は財団によってダブルでもらっていいものとダメなものがあるので気を付けた方がいいと思います。
MC:アメリカの国から出る奨学金はFAFSAというものですが、ジュニアになると学校からお知らせも来ますし、カウンセラーと話したりすると思います。それ以外にもMeritスカラーシップやNeedスカラーシップといった奨学金がありますよね。
アメリカの奨学金は、成績が優秀な人がもらえるMeritスカラーシップと、お金が必要な人のためのNeedスカラーシップの2つに分かれると思います。Meritスカラーシップは私たちのような外国人はもらいづらいのですが、一部外国人に用意している大学というのがあります。私の知っているところだとリッチモンドやペッパーダイン、チャップマンなどが用意してくれています。Meritスカラーシップは受験した人の上位25%の人がもらえます。なので、ものすごくレベルの高い大学だと難しいですが、少しレベルをさげた大学であればもらえる可能性はあります。そして上位10%にいるともっと高い奨学金がもらえる可能性があります。
国が用意しているFAFSA以外に大学が用意しているお金が必要な家庭向けのNeedスカラーシップがあるんですが、これはなかなかもらえないと思います。お金が払えますという人とお金が払えませんという人がいた場合は、払えないという人は合格率が下がります。これは私が知ってショックだったことですが、払えますと言わないと合格できない場合があります。アーリーデシジョン(通称ED:Early
Decision)といって受かったら絶対に行かなければいけない場合は、払えないで申し込みはできないので、気を付けた方がいいです。
MC:FAFSAは、アメリカ、グリーンカード取得者の学生対象で、毎年10月1日に次年度分の申し込みが開始されます。これは申し込みの早い順に支払われるので、遅ければ遅いほどその枠が減ってくるということですのでお気を付けください。それでは、次にうつりまして、イリノイ州の共通試験がSATからACTに変わりましたが、その影響はあると思われますか?
うちはあまり共通テストについては考えていませんでした。大学に必要なのは基本的に学校の成績、エキストラカリキュラー、エッセイだと思っています。ただ、Meritスカラーシップや日本の大学のためには必要になってきます。アメリカの大学でも必要というところもありますが、共通テストは点数が高ければ合格率が高まるということではなく、ある程度の点数(目安として平均点や中央値より少し上)があれば良いと思っています。
MC:うちはハーパーカレッジに2年通ってから編入しましたが、やはり学生ローンは利率も高いですし、学費をおさえるという意味ではこのような選択もありますよね。ハーパーカレッジだから簡単という訳では決してはありませんでした。高いレベルのクラスもたくさんありますし、ストレートAでなければ編入できないというほどではありませんが、日々の勉強とエッセイがとても重要になってくるのではないかと思います。本日はありがとうございました。
MC:それでは、次に日本の大学進学について、実際にアメリカの中学もしくは高校から日本の大学へ進学された4名の方のインタビューを上映いたします。
MC:それでは、ここから河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザーの丹羽さんに帰国生入試についてお話を伺います。

丹羽さん:
私はアメリカ在住27年目になります。来米後、2006年に米日教育交流協議会を設立しまして、在外子女の日本語教育や帰国する方の受験のサポートなどの仕事をさせていただいております。本日は河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザーという立場でお話をさせていただきます。その他に名古屋国際中学校・高等学校の北米地域担当を務め、帰国生受け入れ校としての立場にて、東海地方にお帰りになる方のサポートをさせていただいており、シカゴ地域からお帰りの方も何名か編入いただいております。河合塾海外帰国生コース北米事務所としてはコロナ前までは、帰国生大学入試説明会実施のため、毎年お邪魔させていただいておりました。27年間のアメリカ生活では、カリフォルニア州、ニュージャージー州、ミシガン州、そしてまたカリフォルニア州へと引越しをしました。現在はサンディエゴの補習校の教員を務めておりまして、指導教諭という先生方のスーパーバイザー的なポジションと進学指導を担当し、高校生の指導にもあたっております。補習校の教員は、引越しする中でそれぞれの州で経験をしておりまして、サンディエゴは7年目になりますが、その前はミシガン州のデトロイト近郊に住んでおりましたので、デトロイト補習校でも教員をしておりました。本日は河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザーとして帰国生大学入試のお話をしますが、その他の大学入試や中学・高校入試についてのお問い合わせも個人的にお受けすることもできますので、今後ともよろしくお願いします。
■日本の大学に進学する方法
それでは、まず日本の大学に進学するには、どのような方法があるかをご説明させていただきます。海外に在住している高校生にとっては、多種多様な方法があります。まず、一つ目は、本日お話しさせていただく帰国生入試です。海外就学経験者入試と呼ぶ大学もありますが、こちらは現地校で学ばれた方が対象になる入試です。最近は帰国生入試を廃止するといった大学が増えてきています。早稲田・慶應義塾といった大学も一部の学部・学科を除き廃止しています。そのため、外国人留学生入試という入試を受験するケースもあります。こちらは留学生を対象にした入試なのですが、国籍を問わないという大学もあり、日本国籍でも現地校を卒業していればこの方法で大学受験をすることができる場合があるからです。
希望する日本の大学の帰国生入試が廃止された場合でもこちらの方法で受験し進学している方もいらっしゃいます。一方、現地校を卒業していない場合、帰国生入試を受験できない大学もありますので、その場合は、総合型選抜、AO入試・グローバル入試とも呼ばれる入試で受験できます。現地校を卒業した場合でも受験資格がありますので、帰国生入試を実施していない大学・学部をこの方法で受験することもできます。また、最近は日本の高校でも国際バカロレア(IB)プログラムを導入しているところが増えておりまして、国際バカロレア(IB)入試を実施する大学も増えております。特に帰国生入試の実施が少なく、なかなか合格が難しい医学部、歯学部・薬学部といった医歯薬系の学部がこの入試を導入していることもあり、この入試を受験して進学している方もおられます。実は、国内生の受験方法も様変わりしておりまして、これまでは一般入試で受験する場合がほとんどでしたが、最近は学校推薦型選抜や総合型選抜で入学する学生が半分ぐらいだということです。
以上の入試方法は、入学後は日本語で学ぶということになりますが、最近では入学後に英語での授業を受けて卒業できるという英語学位取得プログラムが続々登場しており、海外で生まれたり、海外の生活が長い高校生や日本語より英語が得意、または帰国後も英語力を保持・向上させたいという高校生には、こちらの入試で日本の大学に進む方もいらっしゃいます。
このように海外で学んでいればいろいろな選択肢があり、複数チャレンジすることもできますので、どの方法が自分に向いているかというのを考えていただくため、ご紹介させてもらいました。なお本日は帰国生入試に絞ってお話をさせていただきますので、その他の方法について詳しくお聞きになりたいということでしたら、ご連絡ください。
■ 帰国生大学入試の選考方法
帰国生入試の選考方法には3つのパターンがあります。
一つ目は海外成績重視型で、書類選考を重視するというパターンの入試です。こちらは現地校の成績、SATやTOEFLのスコアなどの出願書類の内容で合否判定が行われるグループです。ただし、書類審査のみという選考方法は国際教養系学部など英語プログラムの大学が中心で、帰国生入試でこのパターンで実施するのは慶應義塾大学(医学部除く)のみであり、このパターンの大学はあまりないと考えていただいて結構です。
二つ目は入試成績重視型です。この入試でももちろん書類も提出しますが、大学で受験する学力試験、つまり筆記試験の得点が合否結果に影響を与えるというもので、このパターンに入る大学が一番多いです。だいたい70〜80%ぐらいはここに入ります。
最後は、海外成績・入試折衷型です。こちらは1次選考が書類審査、そして2次選考が学力試験というパターンで、現地校の成績やSAT・TOEFLの成績も大切だし、プラスそれをクリアしたら学力試験の成績が合否の決め手になるという大学です。
いずれにしても、書類審査を重視する大学はごく少数で入試成績を重視する大学が大半です。帰国生入試で合格を勝ち取るためには、筆記試験、学力試験で合格できる実力をつけなければいけないということになるわけです。
■TOEFLの重要性とSAT
TOEFLは外国人のための英語能力試験で、英語圏の大学でESLの学生が正規授業を受けることができる英語力を判断するのに使われている120点満点のテストですが、帰国生入試においてTOEFLのスコアを必要とする大学が増加しています。まず、出願基準点としてTOEFLのスコアをを利用する大学があります。基準点は概ね60〜70点台ですが、80点台という大学もあります。なお、このような大学では、基準点をクリアしたら、合否判定には使っていません。一方、TOEFLのスコアの提出を必須とし、合否判定に利用している大学もあります。合格基準点は公開されていませんが、河合塾生のスコアから判断すると、東京大学、京都大学、大阪大学などの旧帝大の国立大学につきましては、合格者の多くが110点を超えています。そして、慶応義塾大学・早稲田大学は100点を超えています。MARCHと呼ばれる人気の難関私立大学は80点を超えています。これらの数字が合格の目安になると言えます。
SATはEnglish800点、Math800点の計1600点満点のテストで、アメリカの大学進学に必要な共通テストですが、旧帝大の一部や慶応義塾大といった難関大学がこのスコアの提出を必要としています。こちらも合格基準点は公開されていませんが、河合塾生のスコアから判断すると、東京大学、京都大学など旧帝大に合格した多くが1500点をクリアしています。また慶応義塾大学の合格者の多くは1300点台後半をクリアしているという状況です。
SATのスコアが必須の大学は少ないですが、TOEFLのスコアが必要な大学は多いですので、帰国生入試にとって重要になります。SATは11年生以上からしか受験できませんが、TOEFLは受験できる学年の制限がありませんので、早めに準備されるとよいと思います。
■帰国生大学入試の入試科目
帰国生大学入試でどんな学力試験が行われるかとい言いますと、文系ですと小論文のみというところが増えていますので、小論文プラス面接のみを受験するという受験生も目立ちます。理系学部については、数学と理科プラス面接というところが多く、小論文を課す大学もあります。
理系学部の数学・理科は日本の高校数学・高校理科のカリキュラムに沿って日本語で出題されます。つまり、日本の数学・理科の入試問題を解いて合格点を取らなければいけないということになります。SATのMathのスコアが高いから、現地校で数学や理科の成績が抜群だから日本の入試問題が解けるというわけでもありません。知識としては現地校で学んだことはとても重要ですが、日本式の受験勉強をしないと合格点は取れませんので、現地校の勉強と同時並行で日本の学習をしておくということが望ましいです。帰国生入試の数学は、数学I・II・III・A・B・Cという6科目から出題されます。現地校では分野別に学びますので、一部の分野を受けなくても卒業単位が取得できます。しかし、日本の大学では全分野から出題されますので、まだ時間があれば、現地校では全分野を履修しておくようにしたほうがよいと思います。また先輩達の話を聞きますと、現地校では良い成績をとっていたけれど、入試問題には太刀打ちできなかった、もっと高いレベル、HonorやAPのクラスを履修しておけばよかったという声も聞いております。したがって、できればHonorやAPといった高いレベルのクラスを履修した方がよいかと思います。GPAは下がってしまいますが、書類選考を重視する大学というのは帰国生入試では少数ですし、アメリカの大学や日本の英語プログラムの大学を受験するというのであればちょっとよろしくありませんが、帰国生入試一本でということであれば、GPA(評定平均値)が多少下がってもそんなに気にすることはありません。むしろ高いレベルの数学を学習するということを心掛けていただきたいと思います。
それから小論文については、なかなか現地にいる間に書けるようになるというのは難しいのですが、時間があればオンライン講座などもありますので、書く練習をしておくことも良いかと思います。海外在住中に心がけていただきたいのは、小論文を書くために必要な知識を吸収しておくということです。小論文では時事問題や社会問題に関する出題をする大学がありますので、日々のニュースをキャッチするということがとても重要です。それから、受験する学部・学科の専門分野に関する出題をするという大学もありますので、自分が受験する学部・学科についての専門分野に関する知識を豊富に蓄える必要があります。ですので、それに関する書籍をたくさん読んでおくということも大切になります。つまり社会問題や時事問題、それから自分の受験する学部・学科の専門に関する知識を得ておくということが大切です。それらの知識がないと何を書いていいか分からないということになってしまいます。小論文は作文力のテストではないので、文章を上手に書くということではなく、自分の意見を論じていかなければなりません。問題解決を提案すること、つまりテーマに潜んだ問題点をどのように解決するかという方法を提案することがゴールになります。キャッチしたニュースや本から得た情報についての問題点を指摘して、その問題点についてどのようにすれば解決できるかという解決策を提案していく練習をしておくことがとても大切になりますので、その点を心がけていただきたいと思います。また課題文として論文を読ませた上で設問に答えていくというような出題形式も増えておりますので、論文を読む練習を積む、一番手っ取り早いのは各新聞社の社説を時間があれば読んでおくとよいでしょう。
英語については、日本の高校英語のカリキュラムに沿った問題、つまり長文読解や英文和訳、和文英訳などを出題する大学が多いですので、過去の入試問題集などに取り組んでおくとよいでしょう。
以上のことを参考にして、海外にいる間から受験対策をしておくことをお勧めします。
■帰国生入試の受験スケジュール(私立大)
帰国生大学入試は、現地校を卒業した年の9月からスタートして翌年の4月入学ということになります。そして私立大学の場合、9月に試験を行う大学が多いですので、ここで合格を勝ち取らないとちょっと焦ってくる、つまり10・11月になると自分の入りたい大学の試験がなくなってくるという可能性もありますので、9月の入試で合格を勝ち取れるようにしていただきたいと思います。6月に帰国して7・8月のこの2か月間しか予備校などで勉強できる期間がありませんので、ここで受験勉強に集中できるように、出願書類の準備を帰国までにきちんと済ませておくということが大切です。出願書類の準備をするということは、結局受験する大学・学部を決めて準備しておかなければいけないということになりますので、海外にいる間に早いうちに受験する大学と学部を決めておくということがとても重要になります。先ほども小論文のところで、自分の学部・学科の専門の知識や情報を得る必要があるとお話しましたが、受験する大学・学部が決まっていなければ出願書類の準備もできませんので、受験が迫った12年生よりもっと下の学年から早め早めに決めておくということが大事だということです。また、総合型選抜(AO入試)は、11・12月あたりに行われます。帰国生はこちらをチャレンジするということもできますし、現地校を卒業できずに帰国し、帰国生入試の受験資格がない場合もAO入試は受験できますので、このぐらいの時期に行われるということをご承知いただければと思います。
■帰国生入試合格のためのポイント
選考方法のところでお話しさせていただきましたように、数学や理科など現地校の勉強が重要な場合もありますので、現地の学習に力をいれていただきたいと思います。また現地校での学習というのは英語で行われますから英語力を上げるためにも現地校の学習はとても大切です。そしてTOEFLやSATのスコアを上げていただきたい。小論文対策として時事問題、社会問題に目を向けること、漢字の勉強も必要です。中学校3年生までで学んだ常用漢字は少なくとも書けるようにしておいていただきたいと思います。理系学部の受験をされる方は理数系科目の受験対策をしっかりしていただきたいと思います。帰国生入試ではSATの受験のように計算機は使えませんので、暗算をスピーディに行うことや公式を確実に覚えることが大切です。そして面接対策も必要です。面接では志望理由を口頭で説明しなければなりませんし、出願時に志望理由書を提出するという大学がほとんどですので、そのためには自分の受験する学部、学科に関する知識を得ることが大事になります。また現在暮らしている国とか都市のことについて、また現地校についても面接で問われることがありますので、それらの知識もしっかり確認しておくということも大事になります。大学・学部を早めに決めて、その大学、学部の情報、また自分が受験したい大学というのはどんな入試を行うのかという入試情報を収集するということがとても大事になりますので、この辺りも合格のポイントになってきます。
そして、親子のコミュニケーションも大切です。ニュースをキャッチするといっても高校生にとっては大変なことですので、親御さんのご協力も必要です。そして志望理由を固めるため、どの大学、どの学部を受けるかというようなことも親子間でお話しされることも帰国生入試では大切かなと思っております。また受験校が決まって、どんな入試をするのか、どんな書類が必要なのかといったことを確認するため募集要項を読み取るといったことも親御さんと一緒にやっていただいた方が間違いがないかと思います。親子一丸となって合格を勝ち取っていくというのが帰国生大学入試だと思っておりますので、その点を念頭においていただければと思っております。
最後になりますが、河合塾ではオンラインで受講できる数学や小論文の講座、夏期講習・冬期講習を実施しております。また、現地校卒業後ご帰国してから学んでいただく大学受験科は、少人数制クラスや個別指導が充実しており、合格率が高いという特長もあります。ウェブサイトやXにも帰国生入試対策に必要な情報が掲載されていますので、こちらもご覧ください。
MC:本日はありがとうございました。
このページの内容は、2025年5月現在の情報提供者の体験談です。毎年内容が変わってくる情報もありますので、参考程度にご活用ください。不明な点は学校区に直接問い合わせされることをお勧めします。何か問題があっても住むトコ.COMは責任を負いかねます。
|